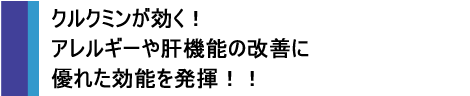|
マリアアザミは、学名はSilybum marianum というキク科の植物で、マリアアザミの他、ミルクシスル、オオアザミ、オオヒレアザミなどと呼ばれます。和名はオオアザミです。原産は地中海沿岸で、ヨーロッパ全土、北アフリカ、アジアに分布しています。葉に白いまだら模様があるのが特徴で、この模様はミルクがこぼれたようにみえるため「ミルクシスル(シスルはアザミの意味)」と言い、ミルクを聖母マリアに由来するものとしてマリアアザミの名があります。
その種子は、ヨーロッパでは古くから民間療法での肝障害の治療薬として利用されていました。マリアアザミの活性成分はシリマリン(silymarin)というフラボノリグナン(flavonolignan)の混合物です。シリマリンには、シリビニン(silibinin), シリジアニン(silydianin), イソシリビン(isosilybin), シリクリスチン(silychristin)などが含まれています。シリビニン(silibinin)はシリビン(silybin)とも呼ばれます。このシリビニン(シリビン)が最も生物活性が高いシリマリン成分です。
1970年代からマリアアザミの種子に含まれるシリマリンを中心に研究がすすめられ、近年、肝細胞保護作用や肝機能改善作用の効果が科学的に証明されています。シリマリンには、肝硬変、慢性肝炎、脂肪肝、アルコール性肝疾患、胆管炎や胆管周囲炎、胆汁うっ滞に効果があり、さらに胆汁の溶解度を高め、胆石を治す効果などもあると報告されています。また、ウイルス性肝炎やアルコール性肝炎あるいは肝硬変の患者を対象にした複数の臨床試験でシリマリンの肝機能改善効果や延命効果が確かめられています。 |